2010年06月25日
生活水タンク改良 その6 一応完成
生活水タンクの改良もそろそろ大詰め。
ようやく殺菌灯が付きましたが、24時間通電する必要はないのでタイマーリレーを使って間欠動作とします。また、水中殺菌灯なので、空気中で使うと故障の元になるらしいく、さらにタイマーリレーを水量検知リレーで制御することにしました。

タイマーリレーはなかなか市販のものでよいものがなかったんですが、ヤフオクで個人製作のすばらしいタイマーリレーを発見。購入後に設定を変えることは出来ませんが、購入時に仕様を指定すれば結構細かい動作にも対応してくれるようです。
今回は、スイッチオンかつリモート入力短絡で1時間待機。10分リレーオンの後6時間待機。以後10分リレーオンの後6時間待機を繰り返し。リモート入力開放でリセットし、再度リモートオンで1時間待機。
というプログラムでお願いしました。
言葉で書くとわかりにくいですが、リモート入力に水位検知リレーを組み合わせます。すると、十分な水位がある場合は1時間の待機の後に繰り返し照射モードに入ります。
水量不足の時はリレーがオフになり、殺菌灯保護のため電源は入りません。
問題はぎりぎりの水量の時で、走行中は水があっちこっちに行くので場合によっては水位検知リレーは頻繁にオンオフを繰り返すことになります。1時間の待機を設定してあるのはこの対策のためで、水位が頻繁に変動する間は照射をしないという訳です。車が止まって水位が落ち着いていて、それでも十分な水位があれば動作に入る、ということです。1日あたり約40分照射と。まぁ、10分くらいの待機でもよかったかなぁとも思いますが、基本的には駐車場に置いているときに定期的に殺菌灯を動作させるための仕組みですからこの辺はアバウトでよいかと。

自作の簡易水位センサーリレー。部品は4点のみです

一応動作してるんでいいんですが、改めてWebで調べてみると、エミッタ接地のNPNトランジスタでスイッチさせる場合はコレクタ側に負荷を接続するみたいですね…。これだからド素人は…OTL
今回はエミッタ側に負荷(リレーコイル)を接続しちゃったんですが(下の回路図)今のところ問題なく動作しているみたい。なにかまずいことが起きるんでしょうか!?
誰か詳しい人教えてください

水位の検出線は小さな端子台でリレーユニットに接続しました。

水位検出リレー、タイマーリレー、蛍光灯のインバータを接続したところ。蛍光灯のインバータはとりあえずここに付けたんですが、銀色の放熱板を短絡させるとまずいらしいので、一応なにかで覆っておくように考えます。
ちなみに殺菌灯関連の電源は、メインオフでも動作して欲しいので下駄箱下のベバストの所から取りました。インバータは共立エレショップの完成品キットです。本当は蛍光管は8Wなんですが、安かった10W2線式を使ってます。出来れば8W4線式を使った方が殺菌灯の寿命は長くなるらしいです。

1時間の待機を待っているのはヒマでしたが、機器設置後1時間して無事に殺菌灯が点きました。
あとは水質検査でもしないと、本当に大丈夫かはわかりませんけども…。
ただ、そもそもこのシステムを考え出されたりびパパさんによりますと、同様のシステムを使用していて大腸菌群と一般細菌の検査をしたところ全く検出されなかった、とのことですのできっと大丈夫です。
ようやく殺菌灯が付きましたが、24時間通電する必要はないのでタイマーリレーを使って間欠動作とします。また、水中殺菌灯なので、空気中で使うと故障の元になるらしいく、さらにタイマーリレーを水量検知リレーで制御することにしました。

タイマーリレーはなかなか市販のものでよいものがなかったんですが、ヤフオクで個人製作のすばらしいタイマーリレーを発見。購入後に設定を変えることは出来ませんが、購入時に仕様を指定すれば結構細かい動作にも対応してくれるようです。
今回は、スイッチオンかつリモート入力短絡で1時間待機。10分リレーオンの後6時間待機。以後10分リレーオンの後6時間待機を繰り返し。リモート入力開放でリセットし、再度リモートオンで1時間待機。
というプログラムでお願いしました。
言葉で書くとわかりにくいですが、リモート入力に水位検知リレーを組み合わせます。すると、十分な水位がある場合は1時間の待機の後に繰り返し照射モードに入ります。
水量不足の時はリレーがオフになり、殺菌灯保護のため電源は入りません。
問題はぎりぎりの水量の時で、走行中は水があっちこっちに行くので場合によっては水位検知リレーは頻繁にオンオフを繰り返すことになります。1時間の待機を設定してあるのはこの対策のためで、水位が頻繁に変動する間は照射をしないという訳です。車が止まって水位が落ち着いていて、それでも十分な水位があれば動作に入る、ということです。1日あたり約40分照射と。まぁ、10分くらいの待機でもよかったかなぁとも思いますが、基本的には駐車場に置いているときに定期的に殺菌灯を動作させるための仕組みですからこの辺はアバウトでよいかと。

自作の簡易水位センサーリレー。部品は4点のみです

一応動作してるんでいいんですが、改めてWebで調べてみると、エミッタ接地のNPNトランジスタでスイッチさせる場合はコレクタ側に負荷を接続するみたいですね…。これだからド素人は…OTL
今回はエミッタ側に負荷(リレーコイル)を接続しちゃったんですが(下の回路図)今のところ問題なく動作しているみたい。なにかまずいことが起きるんでしょうか!?
誰か詳しい人教えてください


水位の検出線は小さな端子台でリレーユニットに接続しました。

水位検出リレー、タイマーリレー、蛍光灯のインバータを接続したところ。蛍光灯のインバータはとりあえずここに付けたんですが、銀色の放熱板を短絡させるとまずいらしいので、一応なにかで覆っておくように考えます。
ちなみに殺菌灯関連の電源は、メインオフでも動作して欲しいので下駄箱下のベバストの所から取りました。インバータは共立エレショップの完成品キットです。本当は蛍光管は8Wなんですが、安かった10W2線式を使ってます。出来れば8W4線式を使った方が殺菌灯の寿命は長くなるらしいです。

1時間の待機を待っているのはヒマでしたが、機器設置後1時間して無事に殺菌灯が点きました。

あとは水質検査でもしないと、本当に大丈夫かはわかりませんけども…。
ただ、そもそもこのシステムを考え出されたりびパパさんによりますと、同様のシステムを使用していて大腸菌群と一般細菌の検査をしたところ全く検出されなかった、とのことですのできっと大丈夫です。
にほんブログ村
2010年06月23日
生活水タンク改良 その5 やり直し
結局コーキング特盛りにしてもダメでしたorz
しかたない、モリモリのコーキングを少しずつはがし、ナットをなんとかひねってとにかく殺菌灯を取り外しました。増設したメンテナンスハッチの場所が悪かったら力が入らずとても無理だったかも。
さぁどうしよう。一番の問題はちょうどいいホールソーがなかったためにドリルソーで開けた穴がいびつな所なんでしょう。きっとそこから漏れているに違いない
対策その1 いびつな穴をプラリペアを使ってなんとか小さくする。
殺菌灯の基部はプラスチック製なので、そのままプラリペアを付けたのでは一体化してしまいます。究極的にはそれもありかもしれませんが、破壊しないと取り外せないのはリスキーすぎます。
とりあえず、殺菌灯が溶剤で溶けないように、自己融着テープを薄く巻き付けれその上にプラリペアを付けてやってみました。
結果……どうにもうまくいきません。ぐるっと順番に周囲に付けている間に、だんだん硬化が進んでしまいます。なんとか溶剤でかたまらないようにしながら穴に突っ込んでみましたが、うまいことかたまるようにするのは至難の業です。
何度か付け方を変えながら試してみましたが、結局あきらめました
対策その2 ブチルゴムでシーリング
なんとかならんかなあと思案して、ブチルゴムでシーリングしてみることにしました。
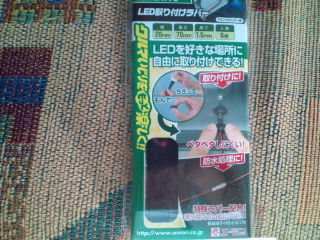
自己融着テープもブチルゴムですが、デッドニングの時に苦労したあのべたべたのブチルゴムならしっかりシーリングできるんじゃないでしょうか。さすがにあのべたべたのをタンクの中に使うのはちょっとイヤなんで、たまたま買ってあったエーモンのLED固定用ブチルゴムを使用。これはテープ状のやつをこねて使うんですが、比較的べたべた感が少ないです。それなりにべたつきますが、手で触っても手にくっついてくるようなことはありません。
とりあえずワッシャー代わりに細くしたブチルゴムを巻いて見ました。が、やっぱり漏れる…。
もうダメじゃん!
と思いましたが、気を取り直してタンクの両側にブチルゴムを付けてみることにしました。
一旦取り外してみると、結構ねじの隙間にもブチルゴムがねじ込まれており、隙間のシーリングとしてはいい感じ。タンク外側には一応もともとパッキンは付いていますが、さらにブチルゴムで強化することに。
水を入れてみました。
・
・
・
・
・
・
・
一応漏れていないみたいです。
そのまま約10時間様子を見ましたが、今のところ漏れなし!


とりあえず仮設置してみました。殺菌灯も点灯させてみましたョ。
殺菌灯はずっと付けている必要はないようなので、タイマーで定期的に動作させる予定です。タイマーはヤフオクでプログラムタイマーをGetしてあります。
ここまでくればもう少しです。殺菌灯が水中にないときは点灯させてはいけないようなので(寿命が極端に短くなるらしい)、水量検知機を作ってタイマーと連動させれば終わりです。
次に総まとめがアップできるといいんですが。
しかたない、モリモリのコーキングを少しずつはがし、ナットをなんとかひねってとにかく殺菌灯を取り外しました。増設したメンテナンスハッチの場所が悪かったら力が入らずとても無理だったかも。
さぁどうしよう。一番の問題はちょうどいいホールソーがなかったためにドリルソーで開けた穴がいびつな所なんでしょう。きっとそこから漏れているに違いない
対策その1 いびつな穴をプラリペアを使ってなんとか小さくする。
殺菌灯の基部はプラスチック製なので、そのままプラリペアを付けたのでは一体化してしまいます。究極的にはそれもありかもしれませんが、破壊しないと取り外せないのはリスキーすぎます。
とりあえず、殺菌灯が溶剤で溶けないように、自己融着テープを薄く巻き付けれその上にプラリペアを付けてやってみました。
結果……どうにもうまくいきません。ぐるっと順番に周囲に付けている間に、だんだん硬化が進んでしまいます。なんとか溶剤でかたまらないようにしながら穴に突っ込んでみましたが、うまいことかたまるようにするのは至難の業です。
何度か付け方を変えながら試してみましたが、結局あきらめました

対策その2 ブチルゴムでシーリング
なんとかならんかなあと思案して、ブチルゴムでシーリングしてみることにしました。
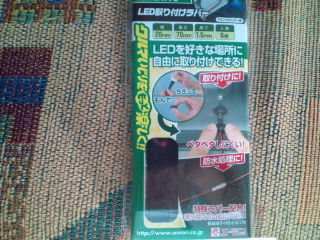
自己融着テープもブチルゴムですが、デッドニングの時に苦労したあのべたべたのブチルゴムならしっかりシーリングできるんじゃないでしょうか。さすがにあのべたべたのをタンクの中に使うのはちょっとイヤなんで、たまたま買ってあったエーモンのLED固定用ブチルゴムを使用。これはテープ状のやつをこねて使うんですが、比較的べたべた感が少ないです。それなりにべたつきますが、手で触っても手にくっついてくるようなことはありません。
とりあえずワッシャー代わりに細くしたブチルゴムを巻いて見ました。が、やっぱり漏れる…。
もうダメじゃん!

と思いましたが、気を取り直してタンクの両側にブチルゴムを付けてみることにしました。
一旦取り外してみると、結構ねじの隙間にもブチルゴムがねじ込まれており、隙間のシーリングとしてはいい感じ。タンク外側には一応もともとパッキンは付いていますが、さらにブチルゴムで強化することに。
水を入れてみました。
・
・
・
・
・
・
・
一応漏れていないみたいです。
そのまま約10時間様子を見ましたが、今のところ漏れなし!



とりあえず仮設置してみました。殺菌灯も点灯させてみましたョ。
殺菌灯はずっと付けている必要はないようなので、タイマーで定期的に動作させる予定です。タイマーはヤフオクでプログラムタイマーをGetしてあります。
ここまでくればもう少しです。殺菌灯が水中にないときは点灯させてはいけないようなので(寿命が極端に短くなるらしい)、水量検知機を作ってタイマーと連動させれば終わりです。
次に総まとめがアップできるといいんですが。
にほんブログ村
2010年06月19日
生活水タンク改良 その4 なかなか進まず
毎日昼にちょいちょいやってるんですがさっぱり進みません。ここ二日の主な状況は……

前回エントリでちょっと触れましたが、タンクの土手っ腹に開けた穴には殺菌灯を付けます。この水中殺菌灯はりびパパさんに教えていただいた三共電気のGLD8MQというやつです。M36のネジが切ってあります。値段は去年買ったんで詳しくは忘れちゃいましたが、1万円強だったかな…

このGLD8MQはある程度長さがあるので途中でステーで支えた方がいい、というのでステンレスのL金具で簡易的ステーを作成。ビニールチューブを緩衝用につけて、タイラップでほどほどに固定する予定。

で、良く見えませんが、増設したハッチから取り付け用に穴をあけました。電動ドリルが入らなかったので手持ちのミニドリルで。めんどくさい…。上から伸びているのは水位検出用電極として使用するコード。単線の銅線でインターホン用ってやつを使いました。


当然水漏れするといけないので、パッキンと水漏れ防止テープを巻いて水漏れ防止を。

殺菌灯を取り付けて、ステーに固定したところです。
さぁ、それじゃぁ、ってんで水を入れてみましたが、どうもちょっとずつ漏れているよう。しょうがない、殺菌灯の寿命はそれなりに長いんで、車の寿命までに付け替えることもなかろうと殺菌灯の周囲をコーキングで固めてしまいました。で、乾燥待ちで翌日再注水。
ところがまだ漏れる。乾いたところでコーキングを撫でてみるとどうも甘いところがあるような…。エイヤッとさらにコーキング特盛。そして再び乾燥待ちの本日です
もう大丈夫だろうなぁ…。穴あけちゃった以上何とかしないと水が入れられませんゾ。今振り返ってみると防水テープの巻きが甘かったのかなぁという気も…。

前回エントリでちょっと触れましたが、タンクの土手っ腹に開けた穴には殺菌灯を付けます。この水中殺菌灯はりびパパさんに教えていただいた三共電気のGLD8MQというやつです。M36のネジが切ってあります。値段は去年買ったんで詳しくは忘れちゃいましたが、1万円強だったかな…

このGLD8MQはある程度長さがあるので途中でステーで支えた方がいい、というのでステンレスのL金具で簡易的ステーを作成。ビニールチューブを緩衝用につけて、タイラップでほどほどに固定する予定。

で、良く見えませんが、増設したハッチから取り付け用に穴をあけました。電動ドリルが入らなかったので手持ちのミニドリルで。めんどくさい…。上から伸びているのは水位検出用電極として使用するコード。単線の銅線でインターホン用ってやつを使いました。


当然水漏れするといけないので、パッキンと水漏れ防止テープを巻いて水漏れ防止を。

殺菌灯を取り付けて、ステーに固定したところです。
さぁ、それじゃぁ、ってんで水を入れてみましたが、どうもちょっとずつ漏れているよう。しょうがない、殺菌灯の寿命はそれなりに長いんで、車の寿命までに付け替えることもなかろうと殺菌灯の周囲をコーキングで固めてしまいました。で、乾燥待ちで翌日再注水。
ところがまだ漏れる。乾いたところでコーキングを撫でてみるとどうも甘いところがあるような…。エイヤッとさらにコーキング特盛。そして再び乾燥待ちの本日です

もう大丈夫だろうなぁ…。穴あけちゃった以上何とかしないと水が入れられませんゾ。今振り返ってみると防水テープの巻きが甘かったのかなぁという気も…。
にほんブログ村
2010年06月11日
生活水タンク改良 その3
毎日ちょっととずつ進展してます
今日は無駄な作業に時間を費やす羽目になりあまりはかどらず。

とはいえ、まずはねじ止めは完了。ただ、用意したねじが若干長かったんですが、掃除の時に気をつけるってことでいいことにしちゃいました。ちなみに鍋タッピングビス12mmを使いましたが、10mmか、いっそ8mmでもよかったかも。
無駄だった作業の片鱗がこの写真にあるんですけど、わかります?通常あるはずのものが何か足りない。
真ん中の棒がないです。一度穴開けのためにタンクを取り出そうかと思い、枠を全部外したんですが、ホースも全部外さないと無理みたいで、スゲー大変そうなのであきらめて戻している途中の写真でした
しかもシートベルトも変なところから出しちゃったのでもう一度外す羽目に…。
枠の付け外しに結構時間がかかり、おまけに電動ドライバーのバッテリーまで消耗してしまったため、予定していた穴開けが途中までとなりました。

途中で止まった穴はこちら。隠れミッキーにあらず。その奥のタンク側壁にも…。

タンク側壁に付けるのはこれです。

今日は無駄な作業に時間を費やす羽目になりあまりはかどらず。

とはいえ、まずはねじ止めは完了。ただ、用意したねじが若干長かったんですが、掃除の時に気をつけるってことでいいことにしちゃいました。ちなみに鍋タッピングビス12mmを使いましたが、10mmか、いっそ8mmでもよかったかも。
無駄だった作業の片鱗がこの写真にあるんですけど、わかります?通常あるはずのものが何か足りない。
真ん中の棒がないです。一度穴開けのためにタンクを取り出そうかと思い、枠を全部外したんですが、ホースも全部外さないと無理みたいで、スゲー大変そうなのであきらめて戻している途中の写真でした

しかもシートベルトも変なところから出しちゃったのでもう一度外す羽目に…。
枠の付け外しに結構時間がかかり、おまけに電動ドライバーのバッテリーまで消耗してしまったため、予定していた穴開けが途中までとなりました。

途中で止まった穴はこちら。隠れミッキーにあらず。その奥のタンク側壁にも…。

タンク側壁に付けるのはこれです。
タグ :清水タンク
にほんブログ村
2010年06月10日
生活水タンク改良 その2
昨日の清掃用メンテナンスハッチ増設の続きです。

充電完了したドリルでガンガン穴あけを進めます。ドリルソーででこぼこをそれらしくならして穴あけ完了。多少でこぼこしてますが、まあどうせ隠れますからね。

ようやくはまるようになりました。ところが、ちょうどいいステンレスのタッピングねじが手元にないことが判明。昼休みに買いに行く時間がなかったので今日はここまで。ほとんど作業が進みませんでした…

充電完了したドリルでガンガン穴あけを進めます。ドリルソーででこぼこをそれらしくならして穴あけ完了。多少でこぼこしてますが、まあどうせ隠れますからね。

ようやくはまるようになりました。ところが、ちょうどいいステンレスのタッピングねじが手元にないことが判明。昼休みに買いに行く時間がなかったので今日はここまで。ほとんど作業が進みませんでした…

にほんブログ村
2010年06月09日
生活水タンク改良 その1
2ndシート下の生活水タンクがどうしても汚れるので、かねてから予定していた改良をようやくはじめることにしました。
まずは内部を掃除しやすいようにメンテナンスハッチの増設から。

購入したのはこちらのもので、ニュージャパンヨットさんから購入。内径16cmくらいのやつなので、元々のより一回り大きいです。

あちこち手が届きやすいようにこの辺に設置することにして、マジックで穴開け位置をマーキング。

こんなに大きいホールソーは持っていないので、地道にドリルソーで穴を開けていきます。残念ながら充電不足だったドリルの電池切れで今日はここまで。
明日は穴開け完了でハッチ取り付けくらいは終わるかな?
まずは内部を掃除しやすいようにメンテナンスハッチの増設から。

購入したのはこちらのもので、ニュージャパンヨットさんから購入。内径16cmくらいのやつなので、元々のより一回り大きいです。

あちこち手が届きやすいようにこの辺に設置することにして、マジックで穴開け位置をマーキング。

こんなに大きいホールソーは持っていないので、地道にドリルソーで穴を開けていきます。残念ながら充電不足だったドリルの電池切れで今日はここまで。
明日は穴開け完了でハッチ取り付けくらいは終わるかな?
にほんブログ村
2010年06月08日
清水が汚い…
2ndシート下の清水タンクなんですが、久々に中を見たら結構汚れてます…。
そもそもここに給水している水が水道水ではなくて、井戸水なのが問題なんですよね

フィルタを通してから給水しているんですが、なんだか茶色くもやもやしたものが…。この水は飲料用には使っていないんですが、あまり気持ちのいいもんじゃないです。何となく土臭いような臭いがするんですよね…。
やっぱり去年から用意だけはしてあったりびパパさん式殺菌灯システムを取り付けないとイカンかな。夏までに、ってもうあまり時間ないね…。タイマー照射とか水位検知リレーとかいろいろ考えてるとなかなか先に進まないなぁ。
そもそもここに給水している水が水道水ではなくて、井戸水なのが問題なんですよね


フィルタを通してから給水しているんですが、なんだか茶色くもやもやしたものが…。この水は飲料用には使っていないんですが、あまり気持ちのいいもんじゃないです。何となく土臭いような臭いがするんですよね…。
やっぱり去年から用意だけはしてあったりびパパさん式殺菌灯システムを取り付けないとイカンかな。夏までに、ってもうあまり時間ないね…。タイマー照射とか水位検知リレーとかいろいろ考えてるとなかなか先に進まないなぁ。
にほんブログ村
2009年11月17日
水量計 その2
水量計製作ですが、だいたいのイメージが完成。

えー、まだ載せてみただけです
こんな感じで2連のレベルメーター(2ndシート下清水タンクとポリタンク用)、満水お知らせブザーを配置します。そのほか、排水タンクもうすぐいっぱいLED、メインスイッチインジケーターLEDを付け、スイッチング用のトランジスタをごちゃごちゃと付けることになります。
ただ、ここで一つ問題が。あまりにケースをギリギリにしてしまったので、検知用のラインをどこから出すべきか…。何とかスペースが取れるのは右下かな…。ケースからケーブルを直だしにするのは引っ張ってしまったりすると危ない気もしますが、もうスペースがないので仕方ないっす。
その分、2cm x 4cm x 8cmとかなり小型に仕上がる予定。
検知用のラインには、LANケーブルを流用する予定です。後は、水につける部分をどういう風に作るか…。側面にボルトで付けるようにするか、何か棒に付けてタンクの天井から下げる形にするか。取り付けが簡単なのはつり下げ型ですかね。ポリタンクにも応用しやすそうだし。
LEDが表に見えるように、ケースに穴を開けるのがまた一苦労なんですよねぇ。何かいい方法ありませんでしょうか。
できあがるのはいつになるやら。

えー、まだ載せてみただけです

こんな感じで2連のレベルメーター(2ndシート下清水タンクとポリタンク用)、満水お知らせブザーを配置します。そのほか、排水タンクもうすぐいっぱいLED、メインスイッチインジケーターLEDを付け、スイッチング用のトランジスタをごちゃごちゃと付けることになります。
ただ、ここで一つ問題が。あまりにケースをギリギリにしてしまったので、検知用のラインをどこから出すべきか…。何とかスペースが取れるのは右下かな…。ケースからケーブルを直だしにするのは引っ張ってしまったりすると危ない気もしますが、もうスペースがないので仕方ないっす。
その分、2cm x 4cm x 8cmとかなり小型に仕上がる予定。
検知用のラインには、LANケーブルを流用する予定です。後は、水につける部分をどういう風に作るか…。側面にボルトで付けるようにするか、何か棒に付けてタンクの天井から下げる形にするか。取り付けが簡単なのはつり下げ型ですかね。ポリタンクにも応用しやすそうだし。
LEDが表に見えるように、ケースに穴を開けるのがまた一苦労なんですよねぇ。何かいい方法ありませんでしょうか。
できあがるのはいつになるやら。
タグ :水量計
にほんブログ村
2009年11月12日
水量計を製作中
我が家のコルドバンクスは、2ndシート下に清水タンクを付けています。
この前、給水時の満水検知器は付けましたが、やっぱりレベルメーターが欲しいなあと思ってます。
パイプだけ取り付けて水面の高さを見ている方もいらっしゃいますが、我が家はいつも補助マットを敷いてお座敷状態なので、潜り込まないと水面式だとわかりません。
バンテックパーツセンターをはじめ、いろいろなところから水量計が出ていますが、どれも高いですねー。メーターとセンサーをあわせると安くても10,000円くらいしてます。何でこんなに高いのよ 続きを読む
続きを読む
この前、給水時の満水検知器は付けましたが、やっぱりレベルメーターが欲しいなあと思ってます。
パイプだけ取り付けて水面の高さを見ている方もいらっしゃいますが、我が家はいつも補助マットを敷いてお座敷状態なので、潜り込まないと水面式だとわかりません。
バンテックパーツセンターをはじめ、いろいろなところから水量計が出ていますが、どれも高いですねー。メーターとセンサーをあわせると安くても10,000円くらいしてます。何でこんなに高いのよ
 続きを読む
続きを読むにほんブログ村
2009年01月23日
満水検知器を設置
セカンドシートの下に清水タンクをつけていますが、水位センサーがないため、満水になったかどうかはあふれてみないとわかりません。
車は屋外なのであふれさせても実害はないのですが、水位センサー、というか満水検知スイッチをつけました。
秋月電子の雨降り警報機キットとフロートスイッチ(ノーマルクローズタイプ)を組み合わせました。送料別にしてあわせて約1000円でした。秋月にはついでがあって直接行きましたが、フロートスイッチを買ったところにも電子工作キット(ウォーターアラーム)MK108があるようなので、そちらを使えば送料が片方で済みますね。

今回私は、キットとスイッチの他にプラスチック製のケースとスイッチ付きの電池ボックス(付属の電池ボックスにはスイッチがなかったので)を追加で使用しました、。キットの基板上にはスイッチがあるのですが、ケースに入れてしまったので、スイッチのオンオフのたびにケースの開け閉めするのが面倒だっただけですので、そのままでも特に問題はありません。ケース自体も、ダイソーで小さいタッパーを買ってくれば開け閉めも簡単ですのでそのままでよいかもしれませんね。付属のケーブルだけでもなんとかなりますが、短いので細くてよいからリード線はあった方がよいでしょう。

清水タンクにドリルで穴を開け(確か直径8mmだったかな…)スイッチを設置。ねじ切りがしてあり、水漏れ防止のゴムワッシャも付属です。

ちょっとケーブルが長すぎてごちゃごちゃになってます…。
スイッチオンにして給水開始。ほぼ満水になったところでメロディーが流れて成功を確認できました。
 フロートスイッチ
フロートスイッチ
ノーマルオープンタイプとノーマルクローズタイプの取り扱いがあるようですが、今回はタンクの上に逆さまに付ける形になるのでノーマルクローズタイプを使用しました。
 電子工作キット(ウォーターアラーム)MK108
電子工作キット(ウォーターアラーム)MK108
今回こちらは使っていないので詳細不明ですが、センサーの代わりにフロートスイッチを付ければ動くと思われます。
 コテライザー
コテライザー
ガス式のコードレス半田ごてです。キャンピングカーの中で工作をするのにとても便利です。超おすすめです。結構ガスがすぐになくなってしまうので、予備のガスは必須です。触媒反応のスタート用に別にライターが必要です。このセットにはコテ台が付属してますが、単品で購入した場合、コテ台に電気式の半田ごてでよく使う、スプリングみたいに巻いてあるやつを使ってしまうとプラスチック部分が溶けてしまいます。私は1本だめにしました。お気をつけください。
 ENGINEER コテライザーガス 265ml SK-90
ENGINEER コテライザーガス 265ml SK-90
コテライザーの充填用のガスボンベです。中身はブタンガスのようなので、いわゆるライター用の補充ガスと同じです。メーカーの言うには純度が異なるので専用品以外は使わないように、とされていますが、100円ショップで買ったライター用のガスでも特に問題なく使えています。かえってボンベが小さくてすむので小型の工具箱にも入れやすくて、純正より便利だったりします。
車は屋外なのであふれさせても実害はないのですが、水位センサー、というか満水検知スイッチをつけました。
秋月電子の雨降り警報機キットとフロートスイッチ(ノーマルクローズタイプ)を組み合わせました。送料別にしてあわせて約1000円でした。秋月にはついでがあって直接行きましたが、フロートスイッチを買ったところにも電子工作キット(ウォーターアラーム)MK108があるようなので、そちらを使えば送料が片方で済みますね。
今回私は、キットとスイッチの他にプラスチック製のケースとスイッチ付きの電池ボックス(付属の電池ボックスにはスイッチがなかったので)を追加で使用しました、。キットの基板上にはスイッチがあるのですが、ケースに入れてしまったので、スイッチのオンオフのたびにケースの開け閉めするのが面倒だっただけですので、そのままでも特に問題はありません。ケース自体も、ダイソーで小さいタッパーを買ってくれば開け閉めも簡単ですのでそのままでよいかもしれませんね。付属のケーブルだけでもなんとかなりますが、短いので細くてよいからリード線はあった方がよいでしょう。
清水タンクにドリルで穴を開け(確か直径8mmだったかな…)スイッチを設置。ねじ切りがしてあり、水漏れ防止のゴムワッシャも付属です。
ちょっとケーブルが長すぎてごちゃごちゃになってます…。
スイッチオンにして給水開始。ほぼ満水になったところでメロディーが流れて成功を確認できました。
 フロートスイッチ
フロートスイッチノーマルオープンタイプとノーマルクローズタイプの取り扱いがあるようですが、今回はタンクの上に逆さまに付ける形になるのでノーマルクローズタイプを使用しました。
 電子工作キット(ウォーターアラーム)MK108
電子工作キット(ウォーターアラーム)MK108今回こちらは使っていないので詳細不明ですが、センサーの代わりにフロートスイッチを付ければ動くと思われます。
 コテライザー
コテライザーガス式のコードレス半田ごてです。キャンピングカーの中で工作をするのにとても便利です。超おすすめです。結構ガスがすぐになくなってしまうので、予備のガスは必須です。触媒反応のスタート用に別にライターが必要です。このセットにはコテ台が付属してますが、単品で購入した場合、コテ台に電気式の半田ごてでよく使う、スプリングみたいに巻いてあるやつを使ってしまうとプラスチック部分が溶けてしまいます。私は1本だめにしました。お気をつけください。
 ENGINEER コテライザーガス 265ml SK-90
ENGINEER コテライザーガス 265ml SK-90コテライザーの充填用のガスボンベです。中身はブタンガスのようなので、いわゆるライター用の補充ガスと同じです。メーカーの言うには純度が異なるので専用品以外は使わないように、とされていますが、100円ショップで買ったライター用のガスでも特に問題なく使えています。かえってボンベが小さくてすむので小型の工具箱にも入れやすくて、純正より便利だったりします。
にほんブログ村






















